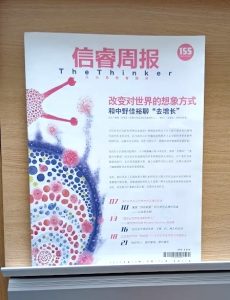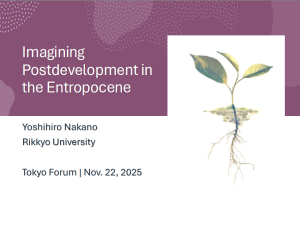2025年11月21日(金)・22日(土)に東京大学に於いて「東京フォーラム2025」という国際シンポジウムが開催されました。数年前より東京大学と韓国・崔鍾賢学術院が共同開催しているイベントです。
今年のテーマは「資本主義を問い直す:多様性・矛盾・未来(Rethinking Capitalism: Varieties, Contradictions, Futures)」でした。現代資本主義世界で起こる様々な諸課題(ナショナリズム、大学教育の危機、気候変動など)に注目し、各パネルで専門家や学生たちが課題や対案などを提示しました。
イベント2日目の午後には「これからの社会変革を編み出す:脱成長とウェルビーイング経済が描く「その先」の社会」というパネル・ディスカッションが設けられました。欧州のエコロジー経済学分野で脱成長論を牽引するヨルゴス・カリス(バルセロナ自治大学)、英国・オーストラリアでウェルビーイング経済の公共政策を提案するキャサリン・トレベック(オーストラリア国立大学)と一緒に、小生も登壇しました。
小生は「Imagining Postdevelopment in the Entropocene」と題して、日本の脱開発論の流れを踏まえた論点を提示しました。。報告スライドは、Researchmapのポータルサイトにアップロードしています。
以下ではその内容を日本語で簡単に要約しておきます。
エントロピー新世の時代における脱開発の構想
Imagining Postdevelopment in the Entropocene
中野佳裕
Yoshihiro Nakano
東京フォーラム2025 (2025年11月22日)
1.はじめに
私は人文学のトレーニングを受けてきた人間なので、「資本主義を問い直す」という大きなテーマに関して、経済学的観点からではなく、むしろメタファーを使ってアプローチしたいと思います。英国の哲学者・作家のアイリス・マードックが述べるように、メタファーは人間の思考の発達にとって非常に重要だからです1。
今回わたしが用いるメタファーは、「ごみ・廃棄物(waste)」です。つまり資本主義経済が人間や人間以外の生命をいかにして廃棄してきたか、重層的な歴史的構造について考えてみたいです。
2.エントロピー新世の大加速化
このパネルの冒頭で、司会の石原先生がプラネタリー・バウンダリー(planetary boundaries)という概念を紹介されました。最新の研究によると、人類が持続的に生存するために維持すべき9つの境界のうち7つの閾値がすでに超えられてしまっているということです。
プラネタリー・バウンダリーを超えてしまった背景には、第二次世界大戦後、特に1950年代以降に始まった「人新世の大加速化」に原因があるとされます。「大加速化」とは、経済活動の地球規模での拡大に応じて地球生態系に対する様々な負荷も幾何級数的に増加した時代のことです。
近年、フランスの技術哲学者ベルナール・スティグレール(Bernard Stiegler)たちは、「エントロピー新世(the Entropocene)」という概念を用いてこの大加速化の時代を説明しようとしています2。工業的経済の発展と大加速化は、エントロピー過程の増大として説明されます。エネルギー・資源の過剰な採掘によって環境は破壊され、工業的生産・消費過程によって生み出される廃熱・廃物は生態系を攪乱し、その結果生じる気候変動や生物多様性喪失などによって人類のみならず地球に存在するあらゆる生命の生存条件が脅威にされされるようになりました。その影響は私たち人間の社会システムや集団心理にも影響を与えるようになっています。
3.熱工業経済と「廃棄された生」ーネガティヴ・コモンズをどう処理するか?
熱工業モデルに依存する資本主義経済は、これまで人間や人間以外の生命を経済成長のための資源として道具化してきました。過去に存在した生産力主義的な社会主義体制や、全体主義のような政治体制も同様です。現代世界は、植民地主義、産業資本主義、帝国主義、全体主義、核の時代、消費社会、そして新自由主義など、生命を経済成長と政治的支配の道具として「廃棄(wasting)」してきた重層的な歴史的構造によって構成されています。
ここに資本主義経済の特徴の一つがあります。一般的に、資本主義経済は商品化・私有化によるコモンズ(共有財・共用地)の破壊を生み出すと言われています。しかし、それだけではありません。産業廃棄物、老朽化し廃棄されたインフラ、廃熱・廃水・内分泌かく乱物質・マイクロプラスティックなどによって汚染された土地・河川・海など、社会や地球の生存にとってマイナスの影響を与え、社会全体でその管理をしていかねばならないような「ネガティブ・コモンズ(negative commons)」を生産します3。つまり、資本主義はコモンズを破壊し、ネガティブ・コモンズを増加させるのです。
このように増加し蓄積されたネガティブ・コモンズは、人間のウェルビーイングを悪化させ、社会の持続可能性を脅かし、さらには地球に存在するすべての生命の「生存可能性(habitability)」を脅かします。
ネガティブ・コモンズとしての廃棄物(waste)は、空間的に不均等に配分されており、植民地主義的な構造を有しており、さらにその影響は地球規模に及びます。(註ー講演では、プラスティックごみによる海洋汚染、マーシャル諸島のルニット・ドーム、福島第一原発事故の汚染土を紹介しました。)
とくに使用済み核燃料などの核のゴミや、マイクロプラスティックは、人間の文明の時間の尺度を超えて存在し続け、地球の地質学的・生物学的時間にまで浸透し続けます。
これらネガティブ・コモンズを生み出す重層的な歴史的構造の各層に対して、どのようにアプローチしていけばよいのでしょうか。これこそが、脱成長やウェルビーイング経済が取り組むべき課題の一つではないでしょうか。
4.脱成長ー「想像力の転換」と「減らす」の弁証法
21世紀初頭にフランスで始まった脱成長運動(décroissance)は、大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式に基づく現代資本主義経済の構造的暴力の克服を目指しています。
その言葉が示す通り、脱成長は地球環境に対する負荷を「減らす」ためにエネルギー・資源の消費を「減らす」、また人間の搾取や不平等を「減らす」ことを目指しています4。
しかし、それだけではありません。フランス語の脱成長には「decroire(経済成長信仰からの脱却)」という含意もあります。つまり、資本主義経済の仕組みを変えるには、経済成長という価値に染まった私たちの想像力の転換5が必要なのです。
「想像力の転換」と「減らす」の弁証法をより活性化させ、あらゆる生命を廃棄する構造的暴力を「減らしていく」という戦略が必要ではないでしょうか。
5.被抑圧者たちの歴史とオルタナティブに注目する
その際、開発や資本主義によって抑圧されてきた被抑圧者(サバルタン)たちの歴史と彼らの内発的なオルタナティブに注目することが重要だと思います。これら被抑圧者の歴史は、脱成長の理念に具体的な内容を与えるものだと、私は考えています。
日本の市民社会の歴史を振り返ると、脱開発・脱成長に近い考えは、近代日本の開発主義や戦争・核の暴力に苦しめられた人々による平和運動の中から生まれました。これら被抑圧者たちの歴史とそこから生まれた平和運動や環境運動は、グローバル・サウス、特にアジア太平洋島嶼部の被抑圧者たちとのグローバルな連帯運動へと発展していきました。
この経験は、欧州の脱成長の言説をより一層多元的にするのに貢献するのではないでしょうか。
5.玉野井芳郎の地域主義の可能性
この視座から見た時、おそらく、玉野井芳郎の地域主義が参照点となるでしょう。玉野井は日本における脱開発・脱成長論の先駆者と言える思想家です。彼が1970年代に提唱した地域主義は、当時の日本の中央集権的で環境破壊的な開発と経済体制に対抗し、分権的でエコロジカルな地域社会の構築を目指しました。その特徴は、非西洋・非近代の多様な経済や技術の役割を再評価した点にあります6。また、ネガティブ・コモンズを減らし、コモンズを再生するような方向で地域主義を考えていました。
玉野井は当時、このような地域主義プロジェクトをボトムアップの運動を通じて実現しよう試みていました。しかし、このような運動が成功するためには、先ほどヨルゴス・カリスが欧州の脱成長運動に関して提案したような、様々な公共政策のサポートが必要となります。
6.脱成長を多元化する
以上の報告で私が主張したかったのは、脱成長を多元化(pluralising degrowth)していくことの重要性です。脱成長は、各地域の文化に応じて多様に描かれていきます。そのためにも、被抑圧者(サバルタン)の歴史とオルタナティブから脱成長を描いていく必要があると思います。
報告を締めくくるにあたって、ジャン=リュック・ゴダールの『愛の賛歌(Eloge de l’amour)』から私の大好きな言葉を引用したいと思います。
Il ne peut y pas avoir résistance sans histoire, sans universalisme. –Jean-Luc Godard
(We cannot have resistance without history and universalism. /歴史と普遍主義がなければ抵抗は存在しない)
ゴダールのこの言葉を、脱成長のために次のように変奏しましょう。
Il ne peut y pas avoir la décroissance sans histoires, sans pluriversalisme.
(We cannot have degrowth without histories, and without pluriverse. /複数の歴史と多元世界がなくては脱成長は存在しない。)
ご清聴ありがとうございました。
以上
中野佳裕
2025.11.30
脚注
脱成長と食と幸福を刊行しました。
脱成長・脱植民地主義・複数の未来
脱成長(白水社クセジュ文庫)